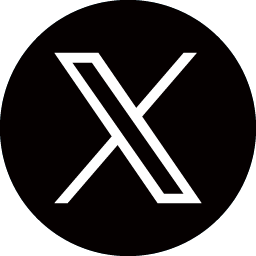基調講演1-1
半導体産業 「強い日本」を目指す
基調講演1-1
半導体産業 「強い日本」を目指す半導体戦略の現状とこれから
経済産業省商務情報政策局情報産業課 課長金指 壽 氏
 招待講演1-2
エッジAIの未来を築く
招待講演1-2
エッジAIの未来を築くArmの戦略
アーム株式会社代表取締役社長横山 崇幸 氏
 基調講演2-1
NVIDIAが見る
基調講演2-1
NVIDIAが見る生成AIの進化
エヌビディア合同会社エンタープライズ事業本部 事業本部長井﨑 武士 氏
 招待講演2-2
富岳NEXT: HPCとAIの融合に
招待講演2-2
富岳NEXT: HPCとAIの融合に向けたプラットフォームへ
慶應義塾大学国立研究開発法人理化学研究所近藤 正章 氏
 基調講演3-3
パナソニックが語る
基調講演3-3
パナソニックが語るAI家電・サービスの最前線
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社くらしプロダクトイノベーション本部 AI・センシング開発部 部長宮嶋 進 氏
 招待講演3-4
GPTはさらなる拡張へ
招待講演3-4
GPTはさらなる拡張へ ~鍵は「エッジ」への浸透~
Kneron Inc.創設者 兼 CEOAlbert Liu 氏
参加特典
視聴&アンケート回答で Amazonギフトカード プレゼント
※条件の詳細は視聴ページ内にある案内をご確認ください ※AmazonはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です
エッジでの
生成AI活用を
可能にする
エッジAIの
導入はどこまで
進んでいるのか
AIの電力
問題解決の
糸口は
AI(人工知能)は加速度的に普及し、今や「AI」という言葉を聞かない日はないほどです。中でも生成AIの技術進歩は非常に速く、毎日のように新しいモデルやサービスが生まれています。エンドポイントの端末や機器にAIを搭載する「エッジAI」もまた、盛り上がりを見せています。エッジAI開発用/導入用のソリューション、実用化の事例ともに着実に増えていて、エッジAIアプリケーションの確かな広がりを感じられるようになっています。
本イベントでは、エッジAI用ハード/ソフト、AIアプリケーション、AIインフラに焦点を当て、各分野のキープレイヤーが注目すべき技術動向や最新情報をお届けします。
開催概要
- 名称
- エッジAI イニシアチブ 2025
Edge AI Everywhere:
加速する技術深化と実用化の現状 - 会期
- 2025年6月17日(火)~ 6月19日(木)
- 形式
- ライブ配信セミナー
- 主催
- EE Times Japan
- 後援
- 各自治体、関連産業団体
- 参加費
- 無料
- 対象業種
- 製造/ロボティクス、自動車、物流・流通/エネルギー/AI、データセンター、航空宇宙等の業種
- 対象職種
- ハードウェア&ソフトウェア&システムエンジニア設計開発者、研究者、データサイエンティスト、機械学習の研究者、半導体製造装置・材料メーカー・商社のエンジニア、ツールベンダー等
※申込の締切は 2025年6月19日(木)14:00 までとなります。
プログラム
Day1 6月17日(火) テクノロジートレンド
生成AIの発展と普及が加速する中、エッジでの生成AI活用のニーズが急速に高まっている。こうしたニーズに応えられる最新のソリューションと開発状況を紹介する他、大規模言語モデルの研究動向もお伝えする。
オープニング・メッセージ 6月17日(火)9:25~9:30
アイティメディア株式会社 EE Times Japan 編集長 村尾 麻悠子
基調講演1-1 6月17日(火)9:30~10:10
半導体産業 「強い日本」を目指す半導体戦略の現状とこれから
半導体の重要性はますます高まり、各国/地域の半導体支援や投資熱は続いている。日本も「半導体・デジタル産業戦略」をアップデートしながら、今後のトレンドを見据えて戦略と支援を強化し続けている。本講演では、AI関連のプロジェクトなどに焦点を当てながら、日本の半導体戦略の概要や具体例を紹介する。
 経済産業省
経済産業省
商務情報政策局情報産業課 課長
金指 壽 氏1998年 通商産業省入省。スタンフォード大学客員研究員、仏EDHEC ビジネススクールでMBAを取得。2009年より経済産業政策局産業再生課、大臣官房総務課政策企画委員等を歴任。2014年より内閣官房日本経済再生総合事務局企画官、ジェトロ・ロサンゼルス事務所次長、経済産業政策局産業創造課長、大臣官房参事官(情報産業・デジタル経済安全保障担当)等を経て、2022年7月より現職。
招待講演1-2 6月17日(火)11:00~11:40
エッジAIの未来を築くArmの戦略
AIがあらゆる産業と人々の生活を変革する中、エッジAIに求められる役割は今、かつてなく高まっています。本講演では、Armが提供する最新の演算プラットフォームとソフトウェアエコシステムを通じて、IoTからクラウドへとつながるエッジAIの展望と、実環境でのユースケース、革新を支える具体的な技術戦略をご紹介します。
 アーム株式会社
アーム株式会社
代表取締役社長
横山 崇幸 氏Armの日本法人であるアーム株式会社の代表取締役社長として日本事業全体を統括し、セールス、顧客・パートナー支援、ビジネス開発を推進。Arm入社以前、イータス株式会社で代表取締役社長およびアジア・パシフィック地域のセールス統括バイスプレジデントを務めたほか、CSR(現Qualcomm)、Infineon Technologies、AMDにて日本法人の代表やセールス・マーケティングの要職を歴任。
セッション1-2 6月17日(火)11:45~12:15
超低消費Hailoチップで生成AIを活用する
第一世代のHailo8が破竹の勢いでエッジAI市場での地位を固め、この度第二世代のHailo10Hをリリースする運びとなりました。H10Hを活用いただく事で、超低消費で最新の生成AIをエッジで活用いただく事ができます。Hailoのユニークなアーキテクチャー並びに開発環境も含めご説明申し上げます。
 Hailo Japan合同会社
Hailo Japan合同会社
GM・カントリーマネージャー
小嶋 範孝 氏
基調講演1-3 6月17日(火)13:00~13:40
加速する未来への挑戦:Rapidusのチップレット戦略
Rapidusは、最先端のチップレットパッケージ(2.xD, 3D)の設計と製造技術を確立するため、北海道千歳にパイロットラインを構築し、2nm世代の半導体を用いた実装量産技術、設計に必要なデザインキット、チップレットのテスト技術の開発を行います。本講演では、Rapidusにおけるチップレットパッケージ開発の包括的な取り組みについて紹介します。
 Rapidus株式会社
Rapidus株式会社
専務執行役員 エンジニアリングセンター長 工学博士
折井 靖光 氏1986年3月 大阪大学基礎工学部卒業。日本アイ・ビー・エム株式会社 野洲事業所入社、大型コンピューターの実装技術からノートブックコンピューター、ハードディスクなどのモバイル製品のフリップチップを中心とした実装の生産技術・開発に従事。2009年6月 東京基礎研究所に異動し、3次元積層デバイスの研究をリード。2012年8月 サイエンス&テクノロジー部長に就任。2016年7月 長瀬産業株式会社へ入社し、商社における技術の目利き役として活動を開始。2017年4月 社長直下の組織として、NVC室(New Value Creation Office)を立ち上げ、2019年4月より執行役員に就任。2022年12月 Rapidus株式会社へ入社、専務執行役員・3Dアセンブリ本部長に就任。2025年4月 専務執行役員・エンジニアリングセンター長に就任。2012年9月 大阪大学工学部にて博士号取得。2015年10月 IMAPS(International Microelectronics Assembly and Packaging Society) Fellowに就任。2016年3月 IEEE EPS(Electronics Packaging Society)Region 10(Asia) Directorに就任。
セッション1-3 6月17日(火)13:45~14:25
業務効率化から価値創造へ - 生成AIの進化とモノづくりへの実践
生成AI技術の進化が加速する中、モノづくりにおける活用は、単なる業務効率化ツールから新たな価値を生み出すパートナーへとその役割を大きく広げています。本セミナーでは、AIエージェントやVLMをはじめとする最新トレンドをご紹介するとともに、モノづくり現場における効果的な活用事例について具体的に解説します。
 ストックマーク株式会社
ストックマーク株式会社
取締役CTO
有馬 幸介 氏
招待講演1-4 6月17日(火)14:30~15:10
エッジで実現する生成AI:超低電力システムの新時代
生成AIのエッジ展開における最新動向や電力効率・低遅延・スケーラビリティ、特にSWAP-C(サイズ・重量・電力・コスト)制約への対応の重要性についての概要をご紹介。ロボティクスや航空宇宙等の厳しい環境向けに、EdgeCortixの最新AIプロセッサ技術とソフト・ハード統合型アクセラレーション基盤による高性能なエッジAI実現方法を解説します。
 EdgeCortix
EdgeCortix
グローバルセールス担当EVP
ティム・ヴェーリング 氏30年以上にわたり上場半導体企業や新興企業でのリーダーシップ経験を有する。EdgeCortix入社以前は、AI半導体スタートアップMythicでSVP(シニアバイスプレジデント)として市場開拓を主導。SynapticsやLSI社など業界を代表する企業で要職を歴任し、収益成長や市場シェア拡大、Go-to-Market戦略の成功を牽引。シリコンバレーを拠点とし、ドイツや日本での勤務経験を含む国際的な経験も豊富に有する。
セッション1-4 6月17日(火)15:15~15:45
エッジAIがより身近に! ~変わりつつある製造現場の未来~
Copilot PCの普及により、ユーザーがAIを身近に活用できるようになった今、産業分野においてもDeep Learningや生成AIの活用が急速に注目を集めています。本講演では、産業分野で幅広く利用されているIntel CPU搭載の組み込みPCを使用したエッジAIの具体的な活用例を紹介し、実装に向けたソリューションについて解説します。
 東京エレクトロン デバイス株式会社
東京エレクトロン デバイス株式会社
ECBU EC技術本部 AIスペシャリスト
坂田 雅昭 氏
招待講演1-5 6月17日(火)15:50~16:30
大規模言語モデルの多様化と最適化戦略 ~知識の再構築に向けて~
大規模言語モデルの社会への浸透が進む中、新たなモデルが次々と登場し、最適化と多様化が急速に進んでいる。本講演では、大規模言語モデルの進化の系譜も踏まえながら、その技術や研究動向を紹介する。また、言語や特定ドメインへの適応について、国立情報学研究所における大規模言語モデル構築の取り組みの紹介や今後の課題について述べる。
 国立情報学研究所
国立情報学研究所
教授
相澤 彰子 氏国立情報学研究所コンテンツ科学研究系 教授。大規模言語モデル研究開発センター副センター長。1990年 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了(工学博士)。学術情報センター助手、国立情報学研究所助教授を経て2003年より現職。東京大学大学院情報理工学系研究科教授および総合研究大学院大学情報学専攻教授併任。専門は自然言語処理と情報検索。
Day2 6月18日(水) エッジAI インフラ
AIの活用では消費電力の増加が深刻な課題になっている。AIインフラの低消費電力化のためにどのような技術が開発され、適用されていくのかを、データセンター用半導体の製品/開発動向から探る。クラウドからエッジにおけるAIエージェント活用や、AIにおけるセーフティについても取り上げる。
オープニング・メッセージ 6月18日(水)9:25~9:30
アイティメディア株式会社 EE Times Japan 編集長 村尾 麻悠子
基調講演2-1 6月18日(水)9:30~10:10
NVIDIAが見る生成AIの進化
生成AI関連市場は今後も急速な成長が続くことが見込まれている。本講演では、生成AI向けにNVIDIAが提供するプラットフォームの特徴や最新のユースケース、さらに今後到来する「フィジカルAI」の時代に向けた取り組みを紹介する。
 エヌビディア合同会社
エヌビディア合同会社
エンタープライズ事業本部 事業本部長
井﨑 武士 氏1999年 東京大学大学院修了。日本TIにて、プロセッサおよびアプリケーションの開発を経て、ビジネス開発に従事。2015年 NVIDIAに入社し、ディープラーニングのビジネス開発責任者を経て、エンタープライズ事業本部を統括。日本ディープラーニング協会および人工知能学会 理事、NEDO技術委員。
セッション2-1 6月18日(水)10:15~10:55
分散エージェント型マルチモーダルLLMの導入
デル・テクノロジーズの最新AIソリューション、Dell AI Factory with NVIDIAを使用し、エッジデバイスとクラウド上で動作する大規模言語モデル(LLM)の分散エージェントシステムについて紹介します。これにより、リアルタイムでの推論とスケーリングが向上し、企業は大規模データセットを効率的に処理し、複雑なタスクを効果的に遂行できます。
 デル・テクノロジーズ株式会社
デル・テクノロジーズ株式会社
インフラストラクチャー・ソリューションズSE統括本部 AIプラットフォーム ソリューションズ
シニアシステムエンジニア AI Specialist / CTO Ambassador
増月 孝信 氏
招待講演2-2 6月18日(水)11:00~11:40
富岳NEXT: HPCとAIの融合に向けたプラットフォームへ
サイエンスの自動化・高度化により科学研究を加速するAI for Scienceの時代に向け、次世代高性能計算基盤の実現が欠かせない。理化学研究所は、スーパーコンピュータ「富岳」の後継機として、HPCとAIの両分野で世界最高水準の性能達成を目標とした次世代システムの開発・整備を行う「富岳NEXT」プロジェクトを始動した。本講演では「富岳NEXT」プロジェクトの概要について述べる。
 慶應義塾大学 理工学部 教授
慶應義塾大学 理工学部 教授
国立研究開発法人 理化学研究所 計算科学研究センター 次世代計算基盤開発部門 部門長
近藤 正章 氏2003年 東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻修了。博士(工学)。東京大学大学院情報理工学系研究科准教授などを経て、2021年4月より慶應義塾大学理工学部教授。理化学研究所計算科学研究センター次世代計算基盤開発部門部門長を兼務。計算機アーキテクチャ、ハイパフォーマンスコンピューティング、人工知能、量子コンピュータに関する研究などに従事。
セッション2-2 6月18日(水)11:45~12:15
エヌビディアJetsonで実現する組み込み製品動向について
NVIDIA Jetsonはソフトウェア・ディファインドでエッジAIアプリケーション開発を加速させる事ができるSystem on Module(SOM)です。NVIDIAが考えるエッジAIのトレンドの解説、菱洋エレクトロのAIソリューションについてご紹介します。
 菱洋エレクトロ株式会社
菱洋エレクトロ株式会社
ソリューション事業本部 第五ビジネスユニット 専任部長
中村 武士 氏
基調講演2-3 6月18日(水)13:00~13:40
AIエージェントの活用はクラウドから組み込み、そしてAI PCへ
あらゆる企業がLLMやAIエージェントを用いて新たな生産性向上のユースケースを模索する中、スケーリングによる経営破綻のリスクなしにAIを商業化することは容易ではありません。本講演では、「AIに万能なハードウェアは存在しない」理由と、AMDがクラウドから組み込み、そしてAI PCに至るまで幅広くAIを実現する方法についてご紹介します。
 AMD
AMD
AIプロダクトマネジメント担当シニアディレクター
Nick Ni 氏AMDにおいてAIプロダクトマネジメントを担当するシニアディレクターで、AIソフトウェアの製品計画やエコシステム・パートナーシップを統括。最近では、PyTorch、Hugging Face、Stability AI、vLLM、SGLang、OpenAIなどとの連携によって、AIソフトウェアスタックの成熟度を飛躍的に高める重要な成果を達成。トロント大学で修士号を取得。
セッション2-3 6月18日(水)13:45~14:25
AI-Ready エッジソリューション ― オンプレミスのエッジ環境へのAIインフラ導入における課題解決の提案
AIの学習環境が整いつつある中、AI推論環境の導入要望が高まっています。しかし、標準化されたインフラデザインや運用方法が未確立で、特に電力供給と空調が課題となっています。今回、データセンターでの知見をふまえ、エッジ環境対応のソリューションを紹介します。
 シュナイダーエレクトリック株式会社
シュナイダーエレクトリック株式会社
セキュアパワー事業部 事業開発本部 ビジネス ディベロップメント プロフェッショナル
菊池 直樹 氏
セッション2-4 6月18日(水)14:30~15:00
世界のエッジ戦略最前線~SUSE Edgeの事例を紹介
工場での自動化、小売DX、宇宙開発……国内外の事例からエッジ導入効果を読み解きます。SUSEならではのエッジ戦略とコンセプトを解説します。ビジネス成長のヒントがここに!
 SUSE ソフトウエア ソリューションズ ジャパン株式会社
SUSE ソフトウエア ソリューションズ ジャパン株式会社
ソリューションアーキテクト
中尾 拓史 氏
招待講演2-4 6月18日(水)15:05~15:45
データフローアーキテクチャが解決するAI電力問題
AI需要の急増に対応するためにGPUが調達できても電力が足りないという未来が目前に迫っています。今こそAIのために最適な基盤を選択し直す時です。AIのためにゼロから考えられたSambaNovaの再構成可能なデータフローアーキテクチャは、遥かに少ない電力で超高速な学習・推論が可能です。本講演ではSambaNovaの取り組みをご紹介します。
 SambaNova Systems
SambaNova Systems
アジア太平洋地域マーケティングディレクター
林 憲一 氏1991年 東京大学工学部計数工学科卒。同年 富士通研究所に入社し超並列計算機の研究開発に従事。サン・マイクロシステムズ、マイクロソフト、エヌビディアでマーケティングの責任者などを経て、2022年1月よりSambaNovaのアジア太平洋地域でのマーケティングの責任者を務める。信州大学社会基盤研究所特任教授も兼務。
セッション2-5 6月18日(水)15:50~16:20
「ものづくり」を支えるAIインフラデザインとは? ~次世代データセンター・ネットワークで挑むAI課題~
ビジネスで急速に拡大するAIの利活用。セキュリティ対策や人材の確保など、数ある課題の中で避けて通れないのがAIインフラの課題。目的・用途に応じたインフラの整備が企業競争力を左右する重要なものとして注目されています。本講演では、製造業のAI活用例から考える最適なインフラのあり方、またその実現に向けた課題と解決策についてNTTコミュニケーションズが提供する省エネデータセンター、ネットワークやクラウドなどのソリューションのご紹介を交えて解説します。
 NTTコミュニケーションズ株式会社
NTTコミュニケーションズ株式会社
クラウド&ネットワークサービス部 第二サービス部門 担当部長
安藤 博樹 氏
招待講演2-5 6月18日(水)16:25~17:05
エンジニアが知っておきたいAIセーフティ
AI技術が日進月歩で進歩するにつれ、AIが人や社会の安全・安心に与える影響は日に日に高まってくる。自動運転バスやチャットBotなどAIがどんどん便利に使われる流れと並行して、AIによる人身事故や差別、偽情報や世論破壊といった懸念まで、様々なレベルでの危機の表明と、法制度や国際議論による規制・制御の動きが出てきている。本講演ではAIが今後の社会に及ぼす利便とリスク、リスクを防ぎ社会としてAIを御する取り組みの議論について、幅広く紹介する。
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インテリジェントプラットフォーム研究部門 副研究部門長
大岩 寛 氏2005年3月 東京大学 大学院情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 博士課程修了。博士(情報理工学)。2005年4月 産業技術総合研究所に入所。情報セキュリティ研究センター、デジタルアーキテクチャ研究センターなどでの勤務を経て、現職。AIセーフティに関するプロジェクトの主宰に加え、ソフトウェアシステム、情報セキュリティ、ネットワークシステムなどの研究に幅広く従事。
Day3 6月19日(木) エッジAI ユースケース
エッジAIの活用と導入はどの分野で、どこまで進んでいるのか。自動車や家電、エンターテインメント分野におけるAI活用の事例を取り上げ、アプリケーションの広がりを伝える。
オープニング・メッセージ 6月19日(木)9:25~9:30
アイティメディア株式会社 EE Times Japan 編集長 村尾 麻悠子
基調講演3-1 6月19日(木)9:30~10:10
産業用AIが直面する課題 ~業務やモビリティの未来に向けて
人工知能(AI)は自動車業界に革命をもたらし、モビリティと仕事の未来に大きな変革をもたらしています。本稿ではContinental Automotiveの取り組みとビジョンに焦点を当て、産業用AIの課題やビジネス機会を多面的に探ります。具体的には、自動車プロセスへのAIの統合、セーフティクリティカルな用途に向けた共感型AIの開発、生産性の向上などを取り上げます。さらに、AIの展開を成功させるためには信頼性や倫理的配慮、一般ユーザーの受け入れが欠かせないことにも言及します。
 Continental Automotive
Continental Automotive
Head of AI for R&D
ヨルグ・ディートリヒ 氏ドイツ・ボン大学および米国・テネシー大学にて物理学(修士号取得)と天文学(博士号取得)を学ぶ。2019年にデータサイエンティストとしてContinentalに入社。以来、多数のAIプロジェクトにおいて、プロジェクトマネジャーとして活躍。2023年10月から現職。Continental独自のR&Dプロセスの効率や有効性、品質を向上させるためのAIツール/ソリューションの開発と提供を担当。
セッション3-1 6月19日(木)10:15~10:55
AMD製品を活用したEdge AI向けソリューション
AMDが提供する半導体デバイスとツールフローを活用した機能実現の事例として、AMD製品・ツールと親和性の高いOKIアイディエスのPCAS(AIモデル軽量化)によるAI実装のソリューションと、AI実装が可能なハードウェアであるNECプラットフォームズのコンパクトボックス型コントローラ AMD Ryzen™ + Versal™ 搭載モデルを紹介します。
 アヴネット株式会社
アヴネット株式会社
第3統括本部 半導体第2事業部 エンジニアリング部 課長
長内 和久 氏
招待講演3-2 6月19日(木)11:00~11:40
AI時代の自動運転 ~ティアフォーとAI技術への取り組みと活用~
自動運転業界では、日進月歩で技術が進化しています。ティアフォーが開発を主導する自動運転用のオープンソースソフトウェアのAutowareは現在、ルールベースと言われる手法で構築されています。昨今の業界トレンドを鑑みて、様々なAI関連技術をどう活用していくのか、またそれに関してどのような課題があるのかについてお話しします。
 ティアフォー
ティアフォー
CTO R&Dユニット
高島 芳仁 氏ペンシルバニア大学でコンピュータサイエンスと数学の学士、コンピュータサイエンスの修士を修了後、MicrosoftやAmazon/AWS本社で0から立ち上げるプロジェクトを主導。日本のAmazon Pointsチームを率いた後、2022年にティアフォー入社。CTOとしてビジネスと技術の両面でイノベーションを推進し、研究開発部門全体を統括。
基調講演3-3 6月19日(木)13:00~13:40
パナソニックが語るAI家電・サービスの最前線
エッジAIが家電にも浸透してきている。クラウド経由のAIに比べ、消費電力を抑えられ、プライバシーを保護でき、セキュリティ面でも有利なエッジAIは、本質的に家電との相性がよい技術だ。本講演では、AIカメラを搭載した冷蔵庫を開発した技術者が、AI家電やサービスの最新動向を解説する。
 パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
くらしプロダクトイノベーション本部 AI・センシング開発部 部長
宮嶋 進 氏1999年、東京工業大学大学院修士卒。同年、松下電器産業株式会社(現:パナソニック)に入社。デジタルテレビ放送立ち上げから4K高画質スマートテレビまでのテレビ商品開発ならびに先行要素技術開発(高画質アルゴリズム開発など)に従事。先行要素技術開発の活動範囲を白物家電にまで広げ、現在に至る。
招待講演3-4 6月19日(木)13:45~14:25
GPTはさらなる拡張へ ~鍵は「エッジ」への浸透~
エッジAIアクセラレーターを専門に手掛けるKneron。本講演では、エッジAI市場を以前からウォッチしてきたKneronが、エッジAIの技術動向や課題、その課題に応え得るKneronのソリューションや開発ロードマップなどを紹介する。
 Kneron Inc.
Kneron Inc.
創設者 兼 CEO
Albert Liu 氏米カリフォルニア大学ロサンゼルス校にて工学博士を取得。QualcommおよびSamsung Electronics R&D Centerにて主要な研究開発および管理職に従事。2015年、AIの効率化、安全性やアクセシビリティ向上のためにKneronを設立。Liu氏は30件以上の国際特許を保有し、「AI革命の主要プレイヤー」として業界やコミュニティに影響を与えている。
6月19日(木)17:00~17:40 で講演を予定していた Stability AI Shan Shan Wong 氏の講演は、都合により中止となりました。
(5月14日掲載)
オンデマンド ショート講演
オンデマンドセッション
AI × モビリティで次世代を切り拓く
NVIDIAの最新GPUのトライアル環境を提供し、モビリティの開発を加速する「GAT(GPU Advanced Test drive)」の記者発表会ダイジェストと、建機・農機の自動運転を支える「AI画像認識リファレンスECU」の紹介動画を公開します。AIで次世代モビリティの開発現場を支える、ネクスティ エレクトロニクスの取組みをご覧ください。
株式会社ネクスティエレクトロニクス
●講演者、プログラム内容、タイムテーブルが変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●会期後よりアーカイブ配信もいたします。気になるセッションの見直しなど、ご都合にあわせて、ぜひ登録・視聴ください。
※一度の登録で、会期中はどのセッションでもご視聴いただけます。またアーカイブ配信だけを視聴する場合でも、登録いただく必要があります。
※アーカイブ配信の準備が整いましたら、登録者の方にメールでお知らせいたします。
●参加特典の詳細条件については、視聴ログイン後の画面でご確認ください。
※フリーメールアドレスでの登録の方や非就業者の方は対象外とさせていただく場合がございます。
※事務局が不正と判断した場合は対象外とさせていただきます。
※発送時期についてのお問い合わせはご遠慮ください。
協賛
プラチナスポンサー
ゴールドスポンサー
シルバースポンサー
ブロンズスポンサー
後援
地方自治体
山口県/北海道/岩手県/山形県/石川県/三重県/広島県/長崎県/熊本県
関連産業団体
国立研究開発法人情報通信研究機(NICT)/独立行政法人情報処理推進機構(IPA)/ソフトウェア協会(SAJ)/生成AI活用普及協会/日本材料学会/日本シミュレーション学会(JSST)/スマートプロセス学会/日本ロボット学会/エンターテインメントXR協会/日本データセンター協会/組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会/電子情報技術産業協会(JEITA)/日本自動車研究所/日本EDAベンチャー連絡会/SEMI ジャパン/半導体産業人協会/日本機械学会/計測自動制御学会 /重要生活機器連携セキュリティ協議会/モバイルコンピューティング推進コンソーシアム/日本ロボット工業会/日本シーサート協議会/日本半導体製造装置協会/JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)/日本OPC協議会/日本量子コンピューティング協会/量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR)/The Autoware Foundation/量子フォーラム/量子イノベーションイニシアティブ協議会/日本ディープラーニング協会/日本ドローン協会(JDA)/AI・IoT普及推進協会/日本クラウドセキュリティアライアンス/ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会/セキュアIoTプラットフォーム協議会/日本電子デバイス産業協会/中小企業AI活用協会/北海道ニュートピアデータセンター研究会/北海道新産業創造機構/在日ドイツ商工会議所/AIガバナンス協会
プログラム委員会
-
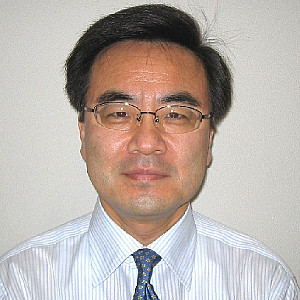 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 招聘研究員
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 招聘研究員
内山 邦男 氏
昨今、生成AIの登場により、AI技術の進展が社会や産業構造に大きな影響を与えつつあります。その礎を築いたヒントン博士が昨年、AI分野でノーベル賞を受賞したことは、AIが世界に与えるインパクトの大きさを改めて印象づけました。この急速な発展は、AIモデルの学習・推論を支えるハードウェアにも変革をもたらし、AIチップの重要性がますます増しています。特にクラウドからエッジまでAI処理が広がる中で、「エッジAI」は今後の成長分野として大きな注目を集めています。本カンファレンスでは、エッジAIに焦点を当て、ハードウェア、ソフトウェア、セキュリティを含む堅実な技術と課題について議論します。本イベントが、参加者の皆様の交流と協創を考え、新たなイノベーションや事業の創造につながることを期待しています。 -
 株式会社ネクスティ エレクトロニクス
株式会社ネクスティ エレクトロニクス
フェロー 博士(工学)MBA デバイスソリューションカンパニー事業開発ユニット 粟島 亨 氏 -
 東京大学大学院工学系研究科
東京大学大学院工学系研究科
教授
池田 誠 氏 -
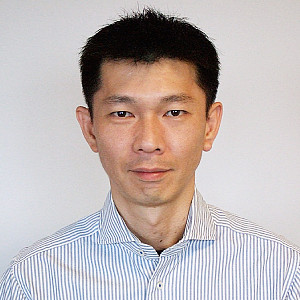 東京科学大学
東京科学大学
教育研究組織 工学院 教授
一色 剛 氏 -
 東京農工大学
東京農工大学
大学院工学研究院
岩崎 裕江 氏 -
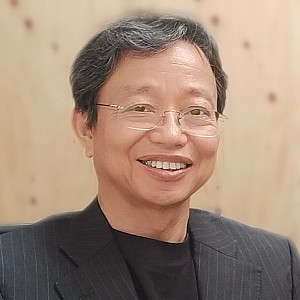 株式会社スキマッチング
株式会社スキマッチング
代表取締役 CEO
岩渕 真人 氏 -
 日本電気株式会社
日本電気株式会社
セキュアシステムプラットフォーム研究所 主任研究員
小林 悠記 氏 -
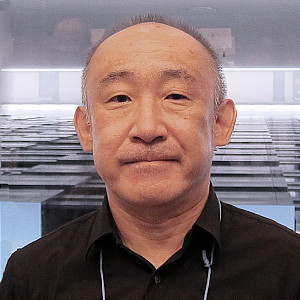 株式会社日立製作所
株式会社日立製作所
研究開発グループ地域戦略統括本部 主任研究員
清水 正明 氏 -
 熊本大学半導体・デジタル研究教育機構
熊本大学半導体・デジタル研究教育機構
准教授
瀬戸 謙修 氏 -
 Advanced Micro Devices Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
アダプティブエンベッデドアンドAIグループ テクニカルマネージャー 立川 研之 氏 -
 インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社
コネクテッドセキュアシステムズ事業本部 IoTインダストリアル部 ディレクター C3(Consumer, Computing & Communication)事業本部 マーケティング部 セントラルマーケティング ディレクター 細田 秀樹 氏 -
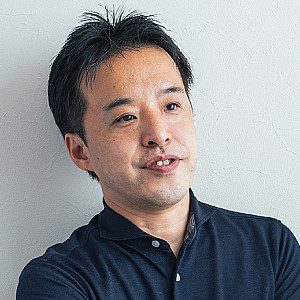 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
イメージング&センシングエッジコア技術部門 SA開発部 シニアシステムアーキテクト 松本 圭司 氏 -
 三菱電機株式会社
三菱電機株式会社
FAシステム事業本部 産業メカトロニクス事業部主席技監 安井 公治 氏
お問い合わせ
アイティメディア株式会社 イベント運営事務局 : event_support@sml.itmedia.co.jp